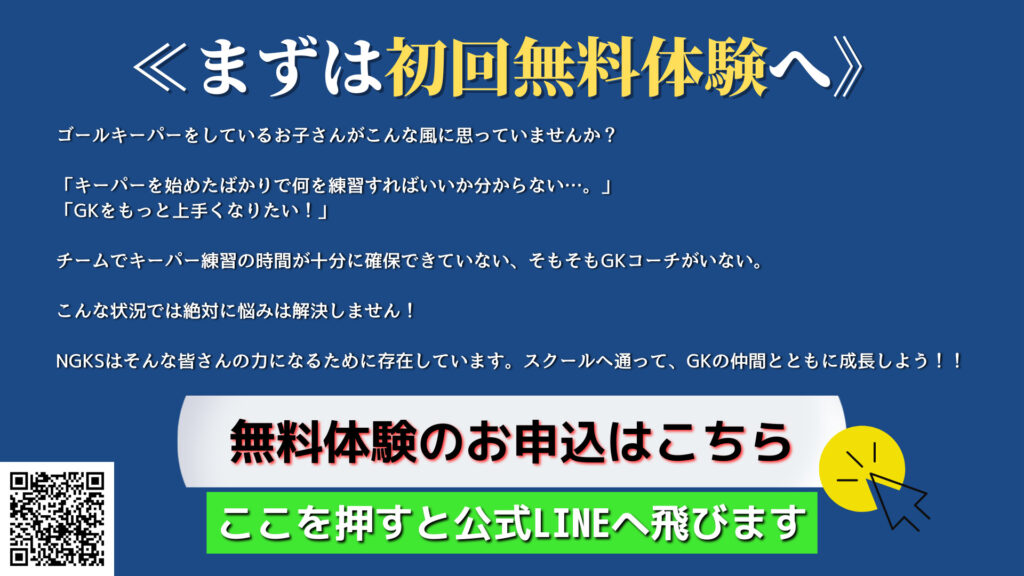おはようございます!
田中コーチです。
-405x270.jpeg)
スクールも3回目となり、少しずつ選手たちにも笑顔や声出しが増えてきました。
環境に慣れ、仲間との関係が築かれてくることで、トレーニングの質も一段と高まってきています。
私たちは技術だけでなく「安心して挑戦できる空気づくり」も大切にしています。
また、礼儀やトレーニングに対する取り組む姿勢にも働きかけており、スクール生としての「あり方」を問うています。
そのうえで一人ひとりの成長に寄り添うことを常に意識しています。
ジャンピングキャッチを極める!
第3回目となる今回のトレーニングでは、「ジャンピングキャッチ」をテーマに実施しました。
クロスボールやコーナキックへの対応など、空中でのプレーはゴールキーパーにとって重要な要素です。
チーム練習では、クロスに出るためのポイントは教えてくれないはず。
長崎ゴールキーパースクールでは、GK専門のトレーニングだからこそ伝えられることがあります。

腕はしっかり上がりますか?
最初に行ったのはスローイング練習です。
両手投げ→オーバーアームスローの順で行いました。
スローインの技術はもちろんですが、ここでは肩甲骨周りの可動域を広げるような意識でトレーニングを行いました。

下半身と上半身を連動させながら、ボールにパワーを伝える動きをできない選手が結構多いです。
単純なスローイング練習ですが、チーム練習や自主練習などで意識してやってみてください。

パワーを伝えられることにより、スローイングの飛距離も伸びてきます。
ゴールキーパーはキックやキャッチも大切ですが、スローイングも大事にしていきましょう。

ジャンピングキャッチのコツ
最初はボールなしでのフォーム確認でした。
助走をつけて高く飛び上がります。ジャンピングキャッチでよくあるミスが、最後の一歩を大きく踏み込めないことです。
走りながら、最後飛ぶ方の足は大きく踏み込むようにしましょう。

また、高く飛ばなければいけないですが、助走の勢いそのままに前に飛んでる選手が結構います。
意識を変えて、上に飛び上がるようなイメージを持ちましょう。

ボールなしで確認をした後は、ボールを持った状態で同じ練習を行いました。
ボールを持つことによって、どこでボールをキャッチするのかという意識を選手たちに持たせました。
ボールをキャッチする場所によって、力の伝わり方が違いますので、自分が一番力を出せる場所でキャッチをしましょう。

実践形式へ
最後に実際にゴール前に立ち、投げられたボールに対してクロスボール対応を行いました。
どこに、どのようにポジションを取るべきかというポイントを話して、守備範囲を広げる意識を持たせました。
練習していく中で、落下地点を予測できない選手が多かった印象です。
空間認知力という力があります。

空間認知力は家でスマホやタブレットを触っているままでは身につきません。
外に出て、体を動かすことでしか身につかないです。私は小学生の時、よく父とキャッチボールをしていました。
そのおかげで空間認知力が鍛えられたと思っています。

最後にその落下地点を予測するためのポイントをお伝えします。
落下地点を予測するために見てほしいものがあります。それはボールの回転です。
回転が縦なのか横なのか。回転数が多いのか少ないのか。
この情報を元にボールのスピードや軌道を予測することができます。

初めてクロスボールの練習を行った選手も多かったと思いますが、今回のポイントを意識しながら
チームでの練習や試合に取り組んでみてください。
最後に映像をどうぞ。
代表 田中